近年、IoTデバイスの発達とともに注目を集める「スーパーシティ(スマートシティ)」。自動運転やキャッシュレス、遠隔医療などを導入しつつ、AIやビッグデータなどを活用して生活全般をスマート化する未来都市で、世界中の国々がその実現に向け実証実験を行っている。日本でも、トヨタが東富士に、あらゆるモノやサービスがつながる実証都市「Woven City」の設置を発表した。ほかにも「国家戦略特区法改正案」、通称「スーパーシティ法案」が成立するなど、今後の動きが注目されている分野だ。
スーパーシティは新分野だけに、どの企業も手探り状態で参入しており、収益化できるかどうか未知数。そんな難しい状況に飛び込んだ1社が、システム開発やサイバーセキュリティーサービス事業を手掛けるITトータルソリューションカンパニーのラックだ。新規事業開発部を立ち上げ、街の安全を⾒衛る事業構想、コードネーム「town」を発表。2022年の実現を目指し動き出している。
先進技術を保有し、セキュリティー分野において盤石な地位を確立しているラックが、リスクをとってこの分野に参入したのはなぜなのか? 旗振り役である又江原恭彦氏に、「town」の構想から参入の理由、これからの「セキュリティー」のあり方について話を聞いた。
取材・文:笹林司 写真:玉村敬太
IoT機器のデータを分析し、街の異常事象を予知・検知するシステム「town」
HIP編集部(以下、HIP):最初に、「town」の概要から教えていただけますか。
又江原恭彦氏(以下、又江原):一言で言えば、街中のセンサーから得られるデータから異常事象を検出し、安全を衛るプラットフォームサービスです。マーケットデータによると、将来的に一人当たり50個程度のIoT機器に囲まれて生活する状態になると言われており、個別に管理・監視することが難しくなることが予想されます。そこで、わたしたちはIoT機器のセンサーから常時データを収集・分析し、異常があった場合は、自治体など「town」を実装する地域の管理者や関連団体と連携します。そうすることで、アクシデントを未然に防いだり、被害を最小限に抑えたりすることができるのです。
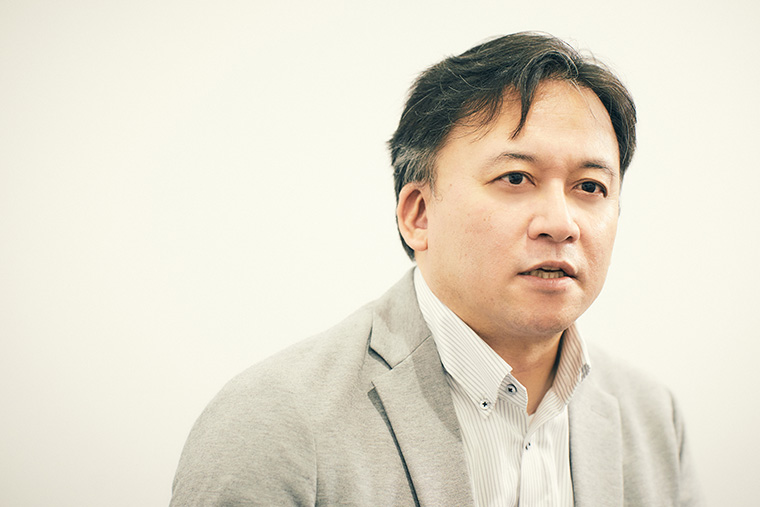
HIP:「街を『守る』」サービスとなると、都市交通、上下水道、福祉などさまざまな領域を横断して関わりがでてくるのではないでしょうか。「town」では、ただ単に仕組みを提供して「守る」だけではなく、我々自身が地域の調査活動や分析技術の研究などを取り組み「衛って」行きます。
又江原:最初は防災・減災の分野から参入することを考えています。河川の水位から氾濫や氾濫区域・経路を予測したり、雨量や地面の状態から土砂崩れを予測したり。市区町村レベルではなく、より細分化された地域の状況を把握できるので、自治体はその情報を利用して、地域にあった避難誘導が可能になります。まだまだ先の話だと思いますが、「town」とドローンやデジタルサイネージを組み合わせ、人々が迷わず安全な道を使用して避難できるよう誘導することが理想です。
あとは、公共交通機関の安全の確保も欠かせないです。いま、自動運転が急速に発達していますが、車単体で安全な自動運転が成り立つとは思えない。道路のセンサーだったり監視カメラだったり、街のインフラと連携してこそうまく機能するものだと考えています。「town」としては自動運転車が安全に走れる公共交通機関をつくりたいですね。
また、個人の安全にも注力したいと考えています。例えば、電気やガス・⽔道などのスマートメーターからデータを収集・分析し、設備の故障や住⺠の⽣命に関わる事故、病気の可能性についてアラートを出します。この情報をもとに、住民の安否確認や救急車の出動などもできるようになるでしょう。

又江原:「town」は、情報を集めて分析するプラットフォーム。いまお話しした例以外にも、「town」を活用する自治体や運営者がどういったスマートシティを目指すかによって、多様な活用方法が考えられますね。
まずはチャレンジする。旭川市での実証実験で見えてきた課題とは
HIP:壮大なサービスですが、すでに実証実験もはじめているそうですね。
又江原:前例のない新しいチャレンジなので、本当に「town」が実装可能なのか、発表する前にいくつかの地域で、IoT機器からの情報収集と分析を実験しました。例えば、2020年の1月から3月に旭川市と協力して行った事例は、積雪対策がテーマです。
じつは、積雪を正確に測るセンサーは驚くほど少ないんです。「積雪は100cm」などという情報が出るのは、自治体の担当者が降雪時に棒を刺して計測しているだけ。想定外の積雪で、一人暮らしのお年寄りが孤立したり、電線や電話線が切れて連絡が取れなくなったりすることも多々あるそうです。
積雪量や積雪時間が予測できれば、事前に避難するなどの対策を打てるはず。そのために実験では、積雪センサーから気温、積雪の変化などのデータが問題なく収集できるか、収集したデータから積雪量・積雪時間の予測ができるかなどを検証しました。

HIP:実証実験で課題など発見はありましたか?
又江原:今回の実験で、製品仕様上は問題なかったはずが、氷点下10度以下でセンサーが不具合を起こすといった事実も発覚しました。また設置箇所の周辺の明かりの状況により正確に計測できない事象も確認しました。これは、やってみないとわからなかったこと。今後も、さまざまなケースの実証実験をやり続けなくてはいけないと実感しましたね。
HIP:長い道のりになりそうですね。
又江原:そもそもが、10年単位の長いスパンで考えている事業構想で、目先の利益は考えていません。まず、2020年度はα版として実証実験を重ね、2021年度に年間を通じた実行可能性の検証(フィジビリティスタディ)を実施。2022年度には、狭い範囲でもいいので、自治体などに実装していただくところまで持っていきたいですね。
インターネットが生活を支える時代。大企業の情報システムを守るだけでは足りない
HIP:IoT機器から情報を得るにはさまざまな事業者が関係するうえに、得られたデータの分析も簡単ではありません。非常にハードルが高い新規事業だと感じますが、そもそも、そういった難しいチャレンジに踏み出した理由を教えていただけますか。
又江原:ラックのサイバーセキュリティーサービス事業は、もともとサイバー攻撃から「国を衛る」という社会的使命感からはじまった事業で、企業の情報システムの構築を請け負うシステムインテグレーションサービスと、情報の安全を衛るセキュリティーソリューションサービスの、ふたつの事業軸を持っています。いずれも大手企業や官公庁がクライアントです。
しかし、会社が設立された1986年当時と比べて、インターネットは個人ひとりひとりの生活に欠かせないものになり、情報漏洩やサイバー攻撃などの脅威が身近なものとなりました。そんな時代にラックとして大企業や官公庁の情報システムだけを守るのは、攻撃者に遅れを取るのではないか。エンドユーザー、つまりは街に生きる人たちこそ衛るべきではないのか。私のように長く業界に在籍しているメンバーには、そういった事業のミッションに基づいた共通の課題意識があった。でも、現業の多忙さで、なかなか一歩を踏み出せずにいたのです。

HIP:ターニングポイントは何だったのでしょう?
又江原:2017年度に現社長である西本が就任したことですね。ラックの創業メンバーであり、長らくCTOを務めていた西本は、先出のような危機意識を持っていました。そこで、就任と同時に「第三の軸となる事業をつくろう。」という方針を打ち立てた。それにともない、2018年に誕生したのが、私の所属する新規事業開発部です。
HIP:そこから「town」を構想するまでの経緯を教えてください。
又江原:「街を衛る」をテーマにすることは自身のなかでは決まっていた。では、どういった方法で衛るのか。何かしらの製品をつくるなど、いまの事業とはまったく異なる領域で勝負するといった議論もあったのですが、やはり20年以上にわたり培ってきたデータ分析・緊急対応の知識・経験を活かすべきだという結論に至りました。
そのなかでも、今後必ず普及するIoT機器に目をつけました。IoT機器を網羅的に管理して通常のデータから異常を見つけ出す、もしくは、異常を予見する。そういったプラットフォームを構築できないか、というアイデアから生まれたのが、「town」です。






