粘り強い啓蒙活動と諦めの悪さが堅実な組織を動かした
HIP:相原さんと川浪さんは、早い段階から新会社の設立も視野に入れていたのでしょうか?
相原:専任部隊をつくるなどして本腰を入れて取り組むべきだとは思っていましたが、当初は新会社の設立までいけるとはさすがに考えていませんでしたね。

川浪:そもそも「ブロックチェーン分会」の時代に、ぼくらが新たなビジネスの種となるアイデアを出しても、それをかたちにしてくれる部署は存在しませんでした。「おもしろいね」というリアクションはあっても、既存の部署業務とは異なる範囲の企画ということもあり、「自分たちがやろう!」とは、なかなかならないんです。
たとえば、ブロックチェーンを使って、ある社会課題の解決を目指すアイデアを企画部門に持っていったものの、業務分掌から外れていると言われてしまい、なかなか先に進めないということがよくありました。
でも、断られたとしても「次はもう少し詰めてきます」とあらためてアイデアを練って説明に行くなどして、社内にぼくらの活動を粘り強く浸透させていきました。
相原:上層部にも社員にも、最初はそこまで響いていなかったかもしれません。でも、フィンテック熱の高まりという外的な要因に加えて、メンバー各自が継続的な啓蒙活動を行ったり、「ブロックチェーン分会」の成果をプレスリリースしたりと、グループ内外での存在感を高めるべく努力していきました。
そうするうちに、勉強会や社内外のセミナーでの発表機会が増え、分会参加者も拡大するなど、徐々に会社全体が注目してくれるようになっていったと感じています。
オンオフ問わずフィンテックのことばかり。熱量が会社を動かした
HIP:「金融イノベーション連絡会」のなかでも、「ブロックチェーン分会」に白羽の矢が立った理由はなんだと思いますか。
宮本:活動内容やタイミングの良さも理由の一つですが、それ以上に活動に対する「熱量」が大きかったと思います。ほかの分会は、所属部署の本業と近い領域での活動がテーマだったため、活動の進捗が本業の繁閑に左右されがちだったのですが、この二人を中心にした当時の「ブロックチェーン分会」は、恒常的に熱量がありましたね。
川浪:どの分会も本業との両立が難しいのは同じなんですが、どの部署の本業からも遠い活動だったからこそ、ぼくらがやらなければという使命感のようなものが共有できていたように思います。そしてなにより、この取り組みの未来をみんなが信じていたというのも大きいですね。
宮本:仕事とプライベートの境目がないくらい、フィンテックに関する話をメンバー間でしていました。飲み会に行っても、川浪や相原は、ずっとブロックチェーンや仮想通貨の話ばかりしていて。
ある意味「フィンテックオタク」みたいな人たちの集まりでした(笑)。そのくらい、活動にのめり込んでいましたね。

川浪:「ブロックチェーン分会」は、飲み会の出席率も高かったですからね(笑)。熱量のあるメンバーばかりでした。
当時は同じ部署にいる人たちよりも、分会のメンバーとのほうが日々話し合っていましたし、なんとか正式に事業化していきたいという強い気持ちを持って活動していました。
大企業からベンチャーへ。アサインが決まったときの葛藤と希望
HIP:グループ内ベンチャーとはいえ、大企業の社員から子会社に移籍するには、不安も大きかったと思います。Fintertechへの参加が正式に決まったときの心境を教えてください。
川浪:分会の活動を本格的に事業化していきたいと望んでいたので、もちろん嬉しさはありました。ただ、15年間ずっと株のトレーダーをやってきて、40歳を前にキャリアをリセットするとなると、やはり少し躊躇しましたね。
また、妻と子どものことも考えると、なかなか踏み切れませんでした。でも、妻に相談したら「ずっとやりたいって言ってたことなんだから、やればいいじゃん。なにを悩んでるの?」って。妻の後押しもあり、責任を持ってやるしかないと前向きに腹をくくりました。
相原:私は、躊躇することはなかったですね。トレーダーから転身した川浪と比較すると、これまでの業務との親和性もありましたので。情熱を注いできたブロックチェーン分会が、新会社設立という次のステップに進むなかで、むしろ自分がそこに入らないのはあり得ないと思っていたくらいです。
「金融イノベーション連絡会」でさまざまな部署の人たちと横断的に交流し、証券ビジネスやグループ全体が置かれている現状や課題も見えるようになっていました。そのなかで、なにかを成し遂げなければいけないという思いもひときわ強くなっていたと思います。
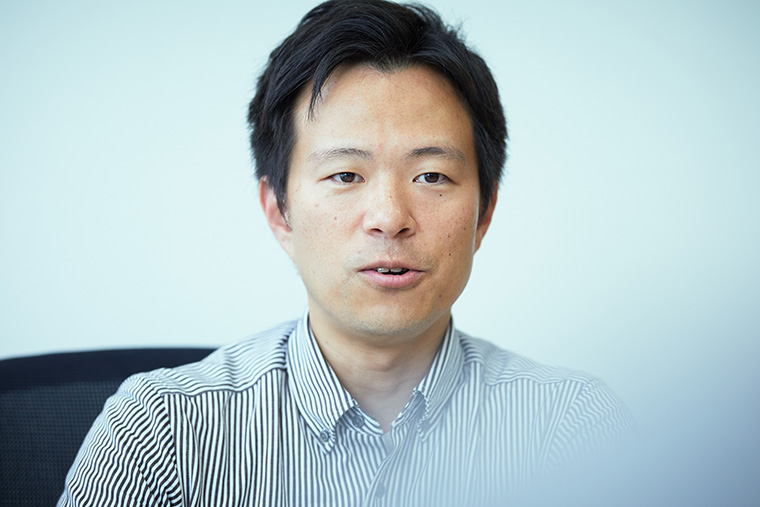
HIP:宮本さんはいかがでしたか。
宮本:正直、少し驚きましたね。私はもともと大和証券で営業を5年経験して経営企画部に異動になったので、二人のように専門的な知識や経験があったわけではありません。
そんな私がFintertechに行ってなにができるのか、という不安はすごくありました。でも、自分と近い世代に向けたサービスを生み出して提供できるのは、個人としても、大和証券グループとしても、視野が広がると思うのでいまでは前向きに捉えています。





