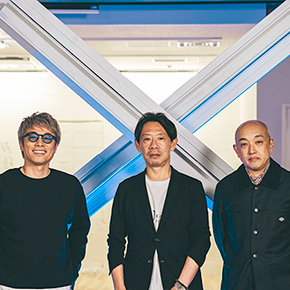『週刊少年ジャンプ』をはじめ、世界的に人気をほこる漫画・アニメコンテンツを輩出してきた集英社の次なる一手がゲーム市場だ。出版とゲーム、業界の垣根を越えて、集英社100%出資の関連会社として「集英社ゲームズ」が2022年に設立された。
集英社のIP(知的財産)を活用したボードゲームシリーズでヒットを生み、オリジナルのデジタルゲームは、国内外の才能を発掘しながら次々と開発が進められている。
出版、そして日本のエンタメコンテンツにおいて不動の地位を確立する集英社が、なぜゲーム領域へと足を踏み入れたのか。そして、そこで活きる集英社の「編集的機能」とは?「原石の輝きを世界へ」を掲げる同社の展望を、Apple 日本支社や集英社での勤務を経て集英社ゲームズを設立し、事業責任者を務める森通治に訊いた。
ゲーム開発の民主化がもたらした新たな可能性
- HIP編集部
(以下、HIP) - まずは集英社ゲームズの事業内容について教えてください。
- 森
(以下、森) - ゲーム事業には、開発を行うディベロッパー、発売元としてゲームの企画・開発から宣伝・販売までを行うパブリッシャーと、大きく2つの役割があり、私たちはパブリッシャーとして事業を展開しています。

- 森
-
現在の事業ラインナップでいうと、『僕のヒーローアカデミア』や『テニスの王子様』、『DEATH NOTE』といった集英社のIPを活用したボードゲームがあり、これらの企画制作・販売を行っています。おかげさまでボードゲームファンと作品ファンの双方に受け入れられ、大ヒット商品になっています。
またデジタルゲームについても、現在開発を進めており、今後リリースしていく予定です。2025年2月13日に発売した『都市伝説解体センター』は、事前のウィッシュリスト登録もかなりの数を集め、リリース前から非常に高い反響を得ていました。デジタルゲームの領域では、集英社のIPにこだわらずオリジナル作品の開発にも注力しているという状況です。

- HIP
- 出版という事業領域からゲームへと足を踏み入れたのは、どのような背景があったのでしょうか?
- 森
-
出版業界全体が変化しているなかで、集英社もデジタルサービスへの移行が進んできています。またアニメビジネスへの投資やライセンスビジネスなど、漫画原作を起点とした副次的なビジネスも展開し始めています。
集英社が持つ資本力や企業ブランド、協業してきたクリエイターとの関係といったアセットを活用できる可能性を検討するなか、エンタメ領域のなかでも圧倒的な規模を誇るゲーム市場に魅力を感じたのが一つの理由です。
さらにUnityやUnrealEngineといったゲームエンジンの普及によってゲーム開発が民主化され、誰もがゲームをつくれるようになったことも追い風でした。こうした時代だからこそ、才能のあるクリエイターを発掘し、ともに作品を作り上げてきた集英社がゲーム事業に参入するのは、非常に意義のあることだと考えています。

『少年ジャンプ』同様、クリエイターへの投資マインドで磨くオリジナル作品
- HIP
- 集英社ゲームズが掲げるミッションについて教えてください。
- 森
-
私たちのミッションは「原石の輝きを世界へ」。パブリッシャーとしてクリエイターの才能を発掘し、しっかりと投資して作品を磨くことが使命です。そして、そうした原石を世界に広げていくことを掲げています。
日本の出版事業やライセンスの展開は、国内市場を対象に行われることがほとんどです。近年では漫画がグローバルに展開されていますが、パブリッシャーが国ごとに異なるケースが一般的です。一方で、ゲームでは全世界への流通を一手に行うことができる環境となっています。世界の市場に直接アプローチするという観点もチャレンジだととらえていますし、エンタメ企業として将来に向けた必要な投資だと思っています。
- HIP
- 出版と同様に「原石の発掘」をゲーム領域で実現するために重視していることは何ですか?
- 森
-
私たちが目指すのは、集英社のIPを広げる観点でゲームをつくるだけでなく、自分たちにしかつくれないオリジナルゲームをつくり、「原作」を生み出すこと。そして、その作品を複合的に展開するアプローチを前提に考えています。
そのためにはクリエイターが本当につくりたいものを尊重し、商業的に成功するようブラッシュアップする役割を果たしていきます。「こういうゲームをつくれば売れる」ではなく、クリエイターがやりたいことや個性に向き合っていくことも大事だと思っています。
大手パブリッシャーでもありながら、個人・小規模なクリエイターの尖ったアイデアを磨く、インディーマインドを持ち合わせた会社だといえますね。
そもそも私たちは新参者ですし、ヒットの法則はあってないようなもの。特定のゲームジャンルや企画に縛られることもありません。未知数な部分が多いなかではさまざまなゲームにトライして、ある意味雑誌のようなポートフォリオの構築を現在は目指しています。

- HIP
- まさに『週刊少年ジャンプ』のような方針。
- 森
-
一つの観点ではそういう見方もあるかもしれません。時代性あるクリエイターの才能とそこから生まれる作品を、ともに磨き上げることがわたしたちのユニークネスになると信じています。商業シーンでのゲーム開発が大規模化してリスクが大きくなるなか、ヒットを確実に狙おうとすると、どんどん均一化されエッジが削られていくことも多くあると聞いています。
もちろん規模の大きなプロジェクトもパートナー企業と共同で行っていきますが、荒削りだけど尖ったアイデアを尊重し、商業的なクオリティを整えていく。そんなバランスを大切にしながら事業全体としてのチャレンジを続けていきたいと思っています。