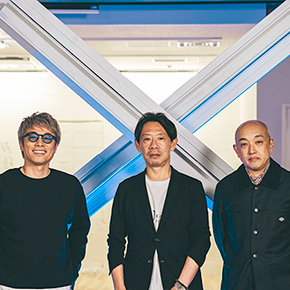苦境にある焼酎業界をブロック紙がサポート。オープンイノベーションプログラムの歩み
HIP:2021年には初のオープンイノベーションプログラム「X-kakeru(かける)」を実施し、外部企業から共同事業のアイデアを募集しています。これも、「共創畑」における大きなチャレンジの一つですね。
清田:はい。これが実現したのも、ビジネス開発局発足からの地道な積み重ねがあったからだと思います。当初はまったくなかったスタートアップとのつながりや新しいビジネスの情報網なども、VCファンドへの出資を機にできたネットワークを生かして徐々に充実していきました。
また、他社の新規事業担当者との横のつながりも生まれ、適宜集まって情報を交換し合っています。こうしたコミュニティーを通じて多くの会社や起業家に「X-kakeru」のプログラムを知っていただけたことが、多くのご応募につながったのだと思います。
ただ、いくら多数の応募をいただいても、私たちの会社にプログラムを運営できるリソースがなければ意味がありません。この点も、うまく社内外を巻き込みながら事務局の体制をつくれたことが大きかったですね。

HIP:具体的に、どのような体制なのでしょうか?
清田:まず、弊社にはこうしたプログラムの経験がなかったため、アクセラレーションプログラムやピッチイベントを実施しているStartupGoGoに運営サポートに入ってもらい、ノウハウを共有していただきました。また、アイデアを採択したりブラッシュアップしたりする過程でもお力添えいただいています。
さらに、ビジネス開発部員だけではなく、グループのさまざまな事業部門にも担当者を置き、横断的な体制で取り組みました。各担当者にはそれぞれがもつアセットの整理、一次・二次審査の選考、最終審査に向けた提案内容のブラッシュアップという過程にも加わってもらいましたね。プログラムを自分事(じぶんごと)化してもらうことで、事業化への近道になると考えました。
このことは事務局の体制を強化するだけでなく、ビジネス開発部だけでは議論の俎上に上らなかった企業の選定、グループ全体での新規事業への意識向上につながったのではないかと思います。また、スタートアップや他社に伴走しながら実際に新規事業をつくっていくプロセスは、異動まもないビジネス開発部員にとっても貴重な経験になったと思いますね。

HIP:最終的に「X-kakeru」では最優秀賞のLocal Local株式会社をはじめ、優秀賞3社、特別賞2社の合計6社の事業が採択されました。これから、どのように事業化を進めていくのでしょうか?
清田:最優秀賞のLocal Localさんとは事業化1号案件として、2022年4月5日に焼酎に特化したウェブメディア「YAKUSAKE(やくさけ)」を立ち上げました。これを基盤として、共同でメディア事業やEC事業を展開していきます。九州産が高いシェアを誇る焼酎は、まさに地域を象徴する文化の一つです。しかし、コロナ禍で大きな打撃を受けていたり、事業承継の悩みを抱えていたりと、業界全体が大きな課題に直面している。
そこで、われわれが販売の一部を担い、地域産業の支援につながればと考えました。ゆくゆくは販売だけでなく、新しい商品づくりや自治体連携など幅広く貢献できるサービスに育てていきたいと思っています。また、Local Localさん以外の5社とも事業化に向けた検討を継続しており、PoCの実施に向けて議論を深めています。

>事業を加速させるには?トップとの近い距離感が大事
HIP:新規事業を推進していくうえで、大事なことは何でしょうか?
清田:挙げればキリがありませんが、なかでも特に大事なファクターが2つあると思います。まずは、当初の構想に固執し過ぎないこと。新規事業って、想定どおりにコトが進むことはほとんどありません。
構想していたビジネスアイデアがなかなかうまくいかないというときには、勇気を持って大きく方向転換することも必要です。特に私たちのようにひとつの事業を長くやってきた会社はそこがなかなか難しいのですが、だからこそアジャイル型で柔軟に対応していくことが大事ではないかと思います。
もうひとつは、社長を含む経営陣の「覚悟」を社内外に示すことです。「X-kakeru」の時も、社内関係者向けに行った事前のオリエンテーション、応募企業向けの対外的な説明会、いずれも社長からメッセージを発信してもらいました。このように、トップ自らがしっかりと意思表示をするかどうかで事業推進のスピード感、クオリティーは大きく変わってくると思います。
また、外部と協業する際にも、こちらが腰の引けた姿勢を見せると向こうは離れてしまう。その事業に本気で向き合う意思を共有するためにも、トップがしっかりコミットしていることをわかってもらうのはとても大事なことだと思います。
HIP:ただ、トップがコミットするといっても、複数のプロジェクトの進捗一つひとつを報告し、承認を得るのはかえって大変ではないでしょうか?
清田:そこは月に1回、社長や役員とビジネス開発部との定例会議で報告しています。その場で「今度、こんな動きをしようと思っています」と提案したり、「ここまでに判断してほしい」といったすり合わせをしたりして、ある程度事前共有したうえで決裁会議にかけているんです。ビジネス開発部も経営陣に丁寧な提案、説明を心がけていますし、トップもこちらを理解しようとしてくれていると実感しています。単に、トップから承諾をもらう、というプロセスに終始していないんです。
ですから、かえってスピードが早くなる。トップとビジネス開発部との、いい意味で「距離が近い関係性」が、うまく機能していると思います。

HIP:最後に、今後の展望をお聞かせいただきたいのですが、今後はどのようなことに注力していくのでしょうか?
清田:そうですね。まずは「X-kakeru」の受賞者や他のパートナー企業と進めている新規事業をしっかりとかたちにすることに取り組んでいきたいと思っています。ただ、それだけではなく、M&Aや資本提携による新たな事業ポートフォリオづくりを通して、グループ戦略に寄与することも、ビジネス開発部の重要なミッションだと考えています。
また、ゆくゆくは再び社内公募で新規事業を募ることも考えています。社内にも、さまざまなアイデアやネットワークを持った社員はたくさんいるはずで、そうした人たちの受け皿をつくっていきたい。そこでアイデアが採択されれば、そのままビジネス開発部に移って、自身で事業化に取り組めるような仕組みの整備も必要ではないかと思います。いずれにせよ、今後も手法やアプローチを限定せず、西日本新聞の新しい姿をお見せしていきたいですね。