主軸となる旅行・テーマパーク・ホテル事業にとどまらず、近年はエネルギーや金融といったチャレンジ領域にも意欲を見せる株式会社エイチ・アイ・エス(以下、H.I.S.)。その一例ともいえるのが、「食品ロス」解消を目指すスマートフォンアプリ「No Food Loss」をリリースした、関連会社のみなとく株式会社だ。
同社代表取締役の沖杉大地さんは、弱冠31歳の若きリーダー。H.I.S.での経験を経て、創業者である澤田秀雄氏が代表を務める「澤田経営道場」に参加し、経営者哲学を吸収してきた。
澤田経営道場は現在、グループから独立した公益法人の運営のもと、社内外から広く人材を募り、次世代リーダーの育成にあたっている。ここでの学びは、事業の立ち上げにどう活かされているのだろうか。そして、事業を担うプレイヤーに贈るべきアドバイスとは何なのか。
今回は第1期生である沖杉さんと、道場設立に尽力し、現在は社外取締役として沖杉さんをサポートする赤尾昇平さんに、お話をうかがった。
取材・文:榎並紀行(やじろべえ) 写真:朝山啓司
きっかけは世界一周。熱い信念だけを胸に、経営者を志すようになった
HIP編集部(以下、HIP):「食品ロス」への社会的関心も高まっていますが、「No Food Loss」はその名もずばりなサービス名ですね。どのようなサービスなのですか?
沖杉大地氏(以下、沖杉):日本では、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品が、年間約643万トンにも達するというデータがあります。「No Food Loss」はそのような食品、たとえば廃棄前のパンやおにぎりなどのクーポンを配布するスマートフォンアプリです。ユーザーはクーポンを使用することで、廃棄前の食品を安く購入することができます。
購入金額の一部は途上国の子どもたちの学校給食支援に充てられ、売上が伸びるほど多くの子どもたちに食料を届けられる仕組みになっています。

HIP:サービス開始から半年が経ちました。反響はいかがですか?
沖杉:リリース以来、さまざまなメディアに取り上げていただき、多くの反響がありました。現状の対応店舗はすべてコンビニチェーン「ポプラ」のグループ店舗なのですが、当初は直営1店舗からはじまり、現在は85店舗にまで拡大しています。
お客さまの反応もよく、いまのところトラブルもなく順調に実績を積み上げられている手ごたえがありますね。最近では、スーパーやドラッグストアなどからもお問い合わせをいただいています。
HIP:沖杉さんは学生時代から起業家を志していたそうですね。
沖杉:学生時代、世界一周の旅をしたのですが、そのとき貧困地域の問題に直面したことがきっかけで、起業に関心を抱くようになりました。

沖杉:そういった地域では、子どもたちが観光客に「ギブミーマネー」とお金をせがんでいた。彼らがもらったお金を握りしめて大人のもとへ走っていく様子を見て、「本当にこれでいいのか」とモヤモヤしていたんです。そんなあるとき、お金ではなくクッキーを渡してみたら、お金よりも遥かに喜んでくれたことがありました。
そのときに、子どもたちが本当に望んでいるのは「マネー」ではなく「フード」なのではないかと感じ、いずれはこうした食の問題を解決する事業を立ち上げたいと考えるようになりました。当時はまだ漠然とした想いだけで、具体的なアイデアはなかったのですが。
澤田秀雄氏の著書に感銘を受け、修行の場として選んだH.I.S.
HIP:卒業後すぐに起業する選択肢もあるなか、H.I.S.に就職した理由というのは?
沖杉:起業への想いはあったものの、それを裏づける経験も知識もなかったので、まずは就職し、会社に貢献しながらビジネスを学びたいと思っていました。
H.I.S.を選んだのは、世界一周の経験を活かせそうだったから、そして同社のベンチャースピリットに惹かれたからです。創業者である澤田秀雄(株式会社エイチ・アイ・エス 代表取締役会長兼社長)の著書を読み、「この人の会社なら、たくさんのことを吸収していずれ自分の力で会社を興せそうだ」と感じました。
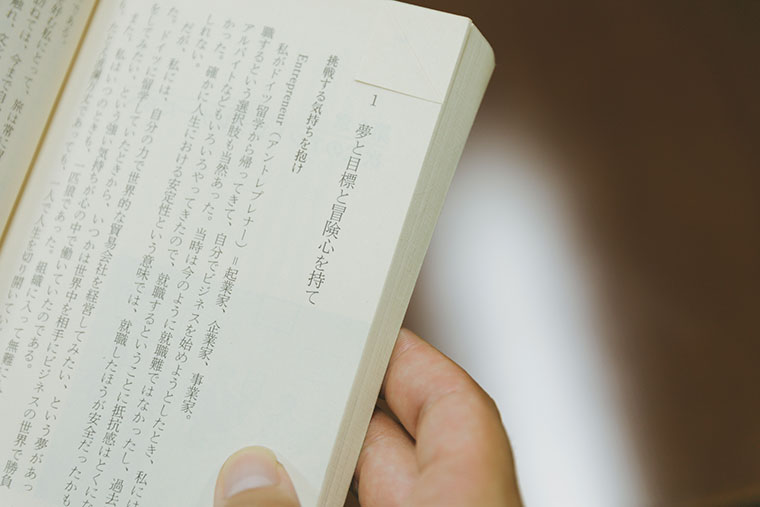
HIP:H.I.S.にはもともと新規事業や社内起業を支援するような制度があったのでしょうか?
赤尾昇平氏(以下、赤尾):社員がエントリーできる社内ベンチャー制度はありました。ただ、それはあくまでH.I.S.内部の新規事業として取り組むもの。別会社として切り出す想定ではありませんでした。
「起業する」というやり方が生まれ始めたのは、2015年に「澤田経営道場」ができてからですね。当時、私は経営企画室で澤田の秘書を務めており、道場の設立にも携わりました。

挑戦する意欲は年齢とともに減ってしまうから、若手の「やる気」を買うべき
HIP:「澤田経営道場」は、そもそもどんな経緯で生まれたのでしょうか?
赤尾:2013年ごろ、澤田から「経営者を育成する道場をつくりたい」という話があり、設立に至りました。経営者としてさまざまな社会課題に触れるなかで、H.I.S.といういち企業を成長させるにとどまらず、「日本を変え、世界で活躍できるリーダーを輩出したい」という想いを強くしていったようです。
社内ベンチャー制度もありましたが、それはあくまでH.I.S.という会社に還元されるもの。澤田はもっと俯瞰的に、「日本、世界に貢献する」という視点で見ていたんですね。道場生に実務で学んでもらう場所として、ハウステンボスを活用できることも大きかったと思います。

赤尾:当時の私の仕事は、澤田のアイデアをかたちにしたり、その進捗を報告したりすることでした。スケジュール管理だけでなく、プロジェクト推進などにも広く携わっていたので、ほかの会社の社長秘書とは少し違うかもしれません(笑)。
「澤田経営道場」も、澤田の計画をもとに、経営学者の野田一夫先生に協力していただきながらかたちにしていきました。当初はH.I.S.社員のみの募集でしたが、第3期からは澤田の「日本中から志を持った人を集めたい」というビジョンを実現すべく、運営元を公益財団法人に移管。中立の立場から、出身を問わず希望者を募っています。
現在は事務局が選考にあたっていますが、1期生のときは、澤田がみずから一人ひとりのエントリーシートに目を通していましたね。

HIP:そして1期生として、沖杉さんを含む10名が選ばれたわけですね。沖杉さんは、なぜエントリーしようと思ったのですか?
沖杉:当時私は26歳で、「経営者になりたい」という夢を買われて経営企画室に所属していました。イチから会社の仕組みや経営を学ばせてもらいましたが、「業務」と「学び」なら、やはり業務の割合のほうが大きかった。「もっと深く勉強したい」という気持ちが膨らんでいたなか、「澤田経営道場」の募集が始まり、気がついたらエントリーシートを書いていました(笑)。

沖杉:正直自信はなかったのですが、「道場生になれなくても、事業を興すという志だけは絶対に捨てない」という気持ちは持ち続けていたんです。選考でも、それだけを伝えました。
赤尾:澤田からは「道場生はできるだけ若手がいい」と言われていました。やはり、部署のキーマンになっているような中堅・ベテラン社員だと、意欲はあっても「自分が抜けて大丈夫だろうか」と考えてしまうと思うんですよね。ですが、若手はあまり考えずに飛び込んでくる。澤田も若手の新しい発想が大好きなんです。
運営側としても、若手の「やる気」を買うべきだと考えていました。経験値がないのだから、できないのは当たり前。経験はあとからついてきますが、挑戦する気持ちや力は、年齢が上がるにつれてどうしても減ってしまいますから。






