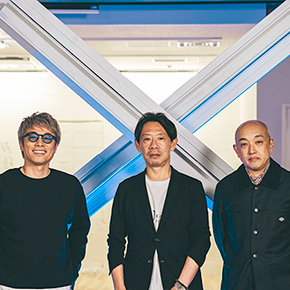高度IT人材の育成とAI開発が強みのスタートアップ2社に出資
HIP:DIF設立と同時に、リカレント教育領域で高度IT人材育成のブートキャンプを提供する「Code Chrysalis Japan」と、AI開発に強みを持つ「Hmcomm」の2社に出資したことを発表されましたね。
水上:Code Chrysalis Japanは、弊社の法人向け学習ソリューションである「Udemy Business」とのシナジーが期待できるスタートアップ企業をリサーチしていて出会いました。
大学・社会人の高スキルIT人材を育成する、ブートキャンプ型のプログラムが日本でも成長することを予測し、ディスラプションとなる企業を探していたんです。その流れで、弊社のUdemy Businessを手がける事業部が、さらなる成長を目指し、Code Chrysalis Japanとの協業を希望しました。
HmcommはAIと音声認識技術を強みにするベンチャー企業です。音声認識処理や自然言語解析処理に関するエキスパートと弊社のデータ分析に取り組む共同プロジェクトチームを発足することで、「進研ゼミ」「こどもちゃれんじ」「学校向けアセスメント」「介護」などさまざまな事業のデータ利活用やAI 開発に役立てられると考え、出資を決めました。

HIP:出資に関しては、スムーズに進んでいったのでしょうか。
杉田:DIFとしては初めての出資でしたが、ベネッセでは以前から出資を行なっていましたので、大きな問題は発生しませんでした。ただ、注意したのは、相手と良い関係を構築しながら契約をまとめられるかという点です。気を配りながら、交渉を進めていきました。
HIP:契約を交わす際、具体的にどういったところを工夫したでしょうか?
杉田:お互いが成長していくというスタンスを出資先に強調して説明しました。出資を検討する際、大企業が出資先のスタートアップに対して、求める要件が細かすぎてうまくいかないというケースが多々あります。
よくあるのが、スタートアップとの共創で生まれた成果物を大企業側が取り上げてしまうというものです。このような過ちを犯さないようにDIFでは、失敗事例をリサーチして対策を練っていたんです。また、弊社の経営層にも出資で起こりうる失敗を共有し、こうしたスタンスに共感してもらっていました。

自前主義のイメージを脱却してスタートアップとの共創を
HIP:水上さん、中村さんが出資先との関係構築において注力された点はありますか?
水上:冒頭でお伝えしたとおり、ベネッセは事業領域が広いのが特徴です。しかし、これまで自前での取り組みが大きいぶん、具体的にどういった技術や情報を所有しているのか外部から理解されていない場合があります。進研ゼミなどの歴史があるサービスでも、どこまでデジタル技術が活用されているのか伝えきれていません。
なので、スタートアップと会話をするときは弊社の既存サービスの裏側までしっかりと説明をしています。出資の目的は事業の創出やサービスの加速なので、スタートアップが持つ技術と弊社のサービスを組み合わせると、どんなシナジーが生まれるのか、アウトプットをイメージできるように、詳細に伝えています。
中村:私はパートナーとのコミュニケーション量を増やすことが重要だと考えています。社内リソースの共有と同様に、われわれが苦手とする部分や弱点も開示して、どのように協力してほしいのか伝えています。
スタートアップからするとベネッセは大企業が陥りがちな自前主義に寄っている部分もあると思います。オープンイノベーションにとって、自前主義はネガティブな要素です。スタートアップとの会話では、われわれが抱える課題を共有して、企業文化を変えていきたいと伝えています。

関わる全員に「よく生きる」を実感してほしい
HIP:これからのDIFのビジョンや目指す方向性を教えてください。
水上:まだDIFというファンドをつくっただけの段階ですので、これからいかに出資対象を広げていくかですね。新しい事業やサービスを誕生させ、DIFの成功事例を増やしていきたいです。
また、ベネッセは人の成長を支援する企業ですので、お客さまだけでなく、DIFに関わった社員もどんどん成長していってほしいという願いがあります。
たとえば、出資したスタートアップ企業にベネッセの社員を出向させたり、逆にスタートアップから人を受け入れたりして、プロジェクトに関わっている全員が成長できるような制度や文化をつくっていきたいです。こうしたサイクルができれば、会社にとっても良い影響が生まれると思いますし、ベネッセらしい取り組みになるのではと期待しています。