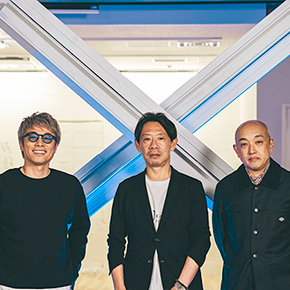たった半年の高速プログラム。「やってみなはれ」がブレイクスルーを生む
- HIP
-
Water Scapeは2025年1月に法人化に漕ぎ着けました。FRONTIER DOJOへのエントリーから、どのくらいの時間がかかったのでしょうか。
- 川崎
-
エントリーしたのは、2023年の秋です。書類審査・面接を通過したあと、半年間のプログラムを経て「免許皆伝」をもらい、未来事業開発部に異動しました。
そこからはWater Scapeの事業に100%集中できることになり、市場調査や事業計画の策定を経て、晴れて会社から出資を受けられることに。2025年1月に登記して、本格的に稼働しはじめたのが4月になります。
- HIP
-
エントリーから本格稼働まで約1年半、スピード感がありますね。FRONTIER DOJO発の事業はどれもそれくらいの速さで進むのでしょうか。
- 後藤
-
商品の製造などが必要な場合は、もう少し時間がかかることもあります。ただ、FRONTIER DOJOが書類・面接審査の通過から最終的な免許皆伝まで、半年間のプログラムであることは変わらないですね。
期間を区切ることで、その期間内にやり残すことがないよう、没頭してもらうようにしています。

- HIP
-
FRONTIER DOJOの運営において、特に大事にしているのはどのようなことでしょうか。
- 後藤
-
「考える」だけではなく、プロトタイプをつくってみる、現場の声を聞くなど、行動を促すことを大切にしています。まさに「やってみなはれ」の精神ですね。
- 川崎
-
私にとってのいちばんの学びも、そこでした。メンターから「本当にそのビジネスモデルが成り立つなら、売れるはず。まずは売ってみてください」と言われ、営業活動を行ったことがブレイクスルーのきっかけの1つでした。
何がよかったかというと、顧客イメージの解像度が飛躍的に上がったのです。当初想定していたニーズは「地下水を持続的・安定的に使い続けたい」という漠然としたものでしたが、実際に想定顧客と話すことで、具体的な困りごとが見えてきました。それによって、どんな商談をしたらよいか、どんなサービスを提供したらよいかがわかってきたのです。
全社で社内起業をサポート。プレゼン時は所属部署の仲間がモニター越しに応援
- HIP
-
ほかに、メンターからの助言で印象に残っているものはありますか。
- 川崎
-
顧客にサービスの導入意欲をたずねるアンケートをとって、よい結果が得られたときのことです。喜んでメンターに報告したら、「アンケートを間に受けてはダメだ」と。「受注したという事実」とアンケート結果には天と地ほどの違いがあり、アンケートだけでは本当に軌道に乗る事業だという証拠にはならないと言われました。
当時は落ち込みましたが、いまとなってはわかります。モニター評価が良かった新商品が売れないことは、よくありますから。
どんな商品・サービスでも「対価を払ってでも欲しい」と思ってもらうことは、とてもハードルが高いことなんですよね。
- HIP
-
現在Water Scapeの事業は、どのようなフェーズですか。
- 川崎
-
きちんと黒字化して、事業として継続できるよう離陸させていくことが目下の課題です。
もちろん、その先に事業を膨らませていくことも考えています。そのためのアプローチの1つが、1社の顧客だけではなく、特定の地域全体に対して水資源の有効活用をサポートすること。それから、国内以上に深刻な水問題を抱えた海外への展開にも、挑戦したいと思っています。
- HIP
-
社内起業家の視点から見て、社内スタートアップ制度に必要なものは何でしょうか。
- 川崎
-
少し抽象的になってしまうのですが、「きちんと魂が込められていること」が絶対に必要だと思います。FRONTIER DOJOは「サントリーから是が非でも新規事業を生み出す。社内起業家を育成する」という、強い思いのもとで設計されています。
そして、その思いをメンターを含む関係者全員が理解して、「愛ある厳しさ」でビシバシ鍛えてくれる。その本気度が、起業家の卵に与える影響は大きいと思います。

- 川崎
-
そしてもう1つは、経営トップの意志です。大企業から生まれる新規事業は、いろいろな部署から既存事業への影響などに関する指摘が入って、進みが遅れたりしがちです。しかしサントリーの場合、FRONTIER DOJOは社長・鳥井信宏の肝煎りプログラムです。
鳥井自身の名で免許皆伝を出し、新規事業への取り組みをきちんと「仕事である」と認めてくれていることは大きいですね。
- HIP
-
全社的に新規事業をサポートする雰囲気は、FRONTIER DOJO参加中にも感じましたか。
- 川崎
-
はい。上司や同僚も理解を示してくれていましたね。最終プレゼン・選考のときは、研究所でパブリックビューイングのようなかたちで応援してくれていたらしく(笑)。免許皆伝が決まると「わーっ」と拍手が起こったとあとから聞いて、とてもうれしく思いました。
量と質を強化してFRONTIER DOJO 2.0へ
- HIP
-
FRONTIER DOJOを運営して得てきた手応えについて、あらためて教えてください。
- 後藤
-
社内に埋もれていたアイデアたちが、FRONTIER DOJOによって陽の目を見るようになったことは大きいですね。
また、残念ながら免許皆伝まで到達できなかった応募案件にも大きな意味があると思っています。「チャレンジしたけどダメだった」は、決して失敗ではない。挑戦したという事実や、そこで得た経験は大きな財産になります。

- 後藤
-
実際、FRONTIER DOJOに参加した社員について、上司らが「考え方が変わった」「姿勢が変わった」などと高く評価することも少なくありません。
- HIP
-
今後の課題についてはいかがでしょうか。
- 後藤
-
エントリーの量と質の改善ですね。量を増やす施策としては、プログラムの説明会、免許皆伝者が体験談を語るイベント、社外の起業経験者の講演会などを各拠点で実施しています。
応募前にアイデアを壁打ちしてブラッシュアップできる窓口なども、拡充したいと思っています。
質の向上は簡単ではありませんが、免許皆伝者たちの事業から成功例が出ることで、応募の中身にもよい影響が出るのではないかと期待しています。
始動してから、約4年。FRONTIER DOJO 2.0とでも言いますか、もう1段階レベルを上げたいですね。それを目指せるフェーズに入ったと思います。