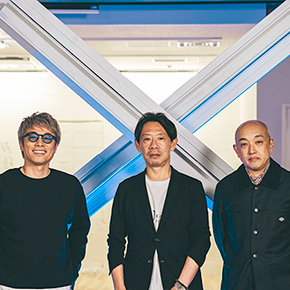これからの銀行は、「信用力」を武器にデータ流通ハブになることで生き残っていく。
HIP:お話を聞いていて、銀行のサービスも大きく変化を求められているということがわかってきました。
大久保:そのとおりです。もともとの銀行の業務は「預金」「融資」「為替」の3つが軸でしたが、いまはこれを一段階広げて、「認証」「スコアリング」「プライシング」といった領域にも取り組んでいます。
具体的に言うと、オンラインバンキングにログインするだけで、それが本人確認の役割を果たして、面倒な手続きなく各種会員サービスに登録ができたり。スコアリングについては、ソフトバンクとみずほ銀行でJ.Scoreという合弁会社をつくりました。利用者の登録する情報に基づき、その方の信頼性や可能性を「スコア」として数値化するサービスで、ソフトバンクでの利用情報やみずほの口座情報と連携していただくことでスコアが上がり、より有利な金利で融資を受けられるようになります。
またプライシングについても、北九州市立大学とBlue Labともう一社で、産学協同研究を行っています。航空券の価格やホテルの宿泊料などでは、AIやビッグデータの予測によって、需要に応じた価格調整がすでに行われていますが、このアルゴリズムを研究し体系化することで、より幅広い商品やサービスに合理的な価格設定ルールを適用することができるようになります。

HIP:「銀行の業務」と聞いて一般の人が想像するよりも、ずいぶん幅広いことに取り組んでいらっしゃるのですね。
大久保:旧来のままではいけないという、危機感からです。これからも銀行が存続しつづけるためには、「信用力」を武器にデータ流通ハブとなって、そのデータを活用しながら融資やコンサルティングを高度化させていかなければならないと思っています。
イノベーションを起こす主体となりうる、若い世代の人々をつないでいきたい。
HIP:最後に、これからお二人が取り組んでいきたいと考えていらっしゃることを教えてください。
片岡:私が取り組みたいのは、「トライセクター・リーダー」の創出、すなわち、官・民・非営利組織のセクター間の垣根を越えてイノベーションを起こす主体となる人をもっと増やしていくことですね。新しいアイデアがあっても、頭の固い周囲の人々に面倒がられて、実現していくのが難しいということはどの組織でもよくあると思います。
けれども、昨今の課題は一組織内だけで解決するには難しいものが多くある。そのようなときのために、組織の内と外、非営利と営利、公的セクターと民間セクターのように、いままでの固定概念によってなんとなく断絶されてしまっていた、20代、30代の若い人たちが協働できるようにつないでいきたいです。
想いを持ったさまざまな人同士が、緩やかに友人としてつながっていれば、お互いの背景事情を理解しあいもっと気軽に意見を交換しあって、その想いの実現に向けて協力しあえる可能性が中長期的に広がっていく。そのためにいまも、学生との意見交換会や、有志でつくった官民若手勉強会(霞が関ラボ)など、若手をつなぐための活動をいろいろと試行錯誤している段階です。
イノベーターと政治の距離も、もっと近いものになればいいなと思っています。事業者が政治家に規制緩和を陳情するというような上下関係のあるものではなく、新しい制度をつくる段階から、最前線で活躍するイノベーターの方々の声を踏まえてたたき台をつくっていく。そうして実装された制度を使ってもらって、新しくて良いアイデアを、より速やかに社会実装できる事例がどんどん出てきてほしいなと思います。このため、制度をつくって終わりではなく、「使ってもらうための営業=政策営業」の視点を持って日々取り組んでいます。

大久保:私はいま一つ、思いを持って取り組んでいることがありまして。「サーキュラーエコノミー」という、リサイクルのようなエコシステムを世の中に広げていきたいと思っています。これまでは、資源を消費してモノをつくり、使い終わったらそれを廃棄する、いわば一方通行な経済のあり方が主流でした。それに対して、製品や部品、資源を回収し、再生、再利用し続けることで、資源の制約を逃れた経済成長をめざす新たな経済モデルがサーキュラーエコノミーです。
これを実現する一つの方法として、「モノ」を「サービス」化するやり方があります。これまで「買う」ことが当たり前だったものを、「時間貸し」にする。例えば海外では、使ったぶんだけ課金するLEDのサービスなどが実用化されています。
EUではサーキュラーエコノミーの実現が経済成長戦略の一つとして位置づけられているなど、世界的な注目度が高まっているなか、日本のメーカーにおいても循環型製品の開発に取り組む必要が出てきていると思います。当然、これはみずほ銀行単体でできることではないので、異業種のクライアントと一緒に取り組んでいきたいです。