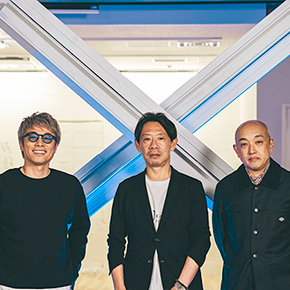審査員は「期待」している
- HIP
- では、主催側から岡さんのプレゼンテーションがどう見えていたかをお伺いしましょう。慶應義塾大学の大岡さんは、医師でありながら、ベンチャー大賞の実行委員を務めていらっしゃいますね。
- 大岡令奈
(以下、大岡) -
ベンチャー大賞は、今年8年目を迎えました。この8年間、さまざまなビジネスコンテストが実施されていますが、毎年ヘルスケアベンチャーに特化して実施してきたコンテストは少ないと思います。
医学部主催というユニークなコンテストだからこそ、審査員はVCの方だけではなく、医師や研究者などサイエンスの観点から審査する方まで揃っています。審査員の方々のコメントは通常、参加者がピッチしたサービスのグッドポイントや今後の課題が挙げられることが多いのですが……。
- HIP
- そうではなかった?
- 大岡
-
デジリハに対するコメントには、「審査とは関係なく、今後に大いに期待する」などと記されていたのが印象的でした。ニーズに対するプロダクトのマッチングの強さを評価するコメントが多く、多くの人の共感を受けたと感じます。

- HIP
- 医療に特化したビジコン」とのことですが、医療領域は専門的な業界だということもあり、参入障壁が高い印象もあります。
- 大岡
- たしかに保守的な業界ではあるので、おいそれとは起業できない土壌はあると思います。だからこそ、それでも起業しようという参加者の皆さんは、ガッツとパッションをもっている方ばかりです。であればこそ、審査の基準としてはパッションだけでなく、ビジネスをスケールさせられるかというスキルも審査員の方々はみています。
- HIP
- そうしたシビアな目の審査員が「期待している」と判断したわけですね。
- 大岡
-
はい。ヘルステックのなかでも、デジリハが取り組んでいるリハビリ分野に挑もうとするスタートアップは決して少なくはありません。医療分野への参入のハードルは相当に高く、創薬領域に至ってはクスリひとつつくるにも膨大な投資が必要になります。その点、リハビリ分野は比較的障壁が低いと考えられています。
競合は「いままでの伝統的なやりかた」
- HIP
- ビジネスをスケールさせるスキル、ということであれば、デジリハはすでに国内47の事業所にも導入されています。むしろビジコンに出るまでもないのではないか、とすら思うのですが。ベンチャー大賞へのエントリーを進めたのは、執行役員の仲村さんだとお伺いしました。
- 仲村佳奈子
(以下、仲村) - ベンチャー大賞がヘルスケアに特化しているというポイントは、やはりわたしたちにとって魅力的に映りました。実は昨年も、ベンチャー大賞にはエントリーしていました。ただし、書類で選考から漏れていたのですが(笑)。

- HIP
- どうして、今年もエントリーをしたのですか?
- 仲村
-
腕試しをするような気持ちもありました。それよりなにより、デジリハの認知を拡げたかったのが大きいですね。ユーザーとなってくれるお客さまだけでなく、起業家、投資家、さらには業界内からの認知はまだまだ足りていないと思っています。
わたしは普段、お客さまとお話しすることが多いのですが、医療や福祉の現場はやはり、保守的です。新参者はもちろん、さらにデジタルをつかった新しい切り口ともなれば、なおさら受け入れられにくいと言わざるをえません。
だからこそ、公正に審査される場でサービスをちゃんと評価してもらうことは信頼につながります。
- HIP
- 評価ということでいうと、ユーザー目線でみたとき「リハビリの良し悪し」を評価するのも難しそうですね。
- 仲村
-
リハビリに対する対価は、一定の医科診療報酬点数で算定されます。ですから、提供する側がどれだけ質が高いリハビリを提供しようが、得られる報酬は同じです。
そうすると、どうしたって内容には質の差が生まれますし、プラスアルファで投資してまでやる必要があるかという話にもなってきます。つまり、あえて競合を挙げるとするなら、「いままでの伝統的なやり方」。リハビリをサービスとする以上、向き合うべきは「それは必要なのか」という疑問なんです。

- HIP
- 「別に同じでいいんじゃない」という声を超える必要があるわけですね。その点で言うと、デジリハが提供してるものって何なのでしょう?
- 仲村
-
わたしたちが追求しようとしているのは、「リハビリ当事者の主体的なリハビリへの参加」です。リハビリを実践する当事者の皆さんが、自分からやりたい活動として参加できてこそリハビリ。そのためにも、「なんとなく」で済まされそうなリハビリを、その効果も含め、ちゃんと「見える化」したいと考えています。
- HIP
- 「見える化」という点では、ベンチャー大賞のユニークさのひとつであるアカデミアとの強い連携がいかせそうです。
- 大岡
-
そうですね。集めたデータを研究として昇華させるプロセスは、アカデミアが得意とする部分です。過去には、エントリーしたアプリ開発者が、本学をはじめとする大学とともに共同研究を進めた事例もありました。スタートアップが事業開発する際、集まった大量のデータを研究成果としてまとめあげる過程で、うまく使っていただけることもあると思います。
- HIP
- 今後は海外展開も考えられているそうですね。
- 岡
-
はい、来年からはインドでの試験導入も始まる予定です。現地の施設でわたしたちのサービスがどのように使われていくか、みていくのが楽しみです。海外のリハビリの現場ではハードウェアメーカーも多く参入していますが、当事者の皆さんはそうしたテクノロジーに対してどうしても萎縮してしまうとも聞いています。
病院で体験したリハビリを、自宅に帰ったときも同じデータ、同じ環境で実践できるシステムをつくること。やはり最終的に追求するのは、リハビリを実践する当事者にとって大きなインパクトをもたらすサービスなのです。