1990年代、テレビ東京で放送されていた『ギルガメッシュないと』。深夜帯の放送ながら時にゴールデンを超える視聴率を出した、伝説的なお色気番組だ。しかし、その高視聴率があだとなり、PTAや婦人会などからバッシングを受けるなど、時代の波に抗えず、打ち切りが決定した。
そんな番組をモチーフにしたドラマ『ギルガメッシュFIGHT』が、2022年12月からParaviで配信されている。圧倒的な熱量を持つ制作チームの手により人気番組となった『ギルガメ』の、熱狂的な盛り上がりから終焉までを描いている。
コンプライアンスの徹底が求められる令和の時代に、過激さや露出をどのように工夫し『ギルガメ』を描いたのか。 『ギルガメッシュFIGHT』のチームを率いた番組プロデューサーの工藤里紗氏の言葉から見えてきたのは、「大企業」の規制から抜けだし、新たなプロジェクトを生み出すヒントだった。
取材・文:榎並紀行(やじろべえ) 写真: 佐藤翔

「攻める」を履き違えたくなかった
HIP編集部(以下、HIP):『ギルガメッシュないと(以下、ギルガメ)』といえば、1990年代に放送されていた伝説的番組です。それから30年が経った令和になって、なぜ『ギルガメ』をテーマにしたドラマをつくることになったのでしょうか?
工藤里紗(以下、工藤):『ギルガメ』は低予算かつ深夜帯の放送ながら、当時の深夜番組としては異例の高視聴率を叩き出していました。
あの番組を生んだつくり手たちの意志や熱量、また、バブルの余韻が残る世の中の狂騒的な空気感は、いまの人たちにも伝わるものがあるのではないか、そんなことを今回のアソシエイトプロデューサーである先輩の濱谷晃一が考え、「『ギルガメ』を使ったコンテンツ」をつくる企画が持ち上がったんです。

HIP:番組をそのまま復活させるのではなく、『ギルガメ』の制作現場を舞台としたドラマというのも面白いアイデアですね。
工藤:ドラマにすること自体は、私に話が来る前の段階で決まっていました。というのも、「令和版ギルガメッシュないと」みたいなかたちで、番組を復活させるやり方は難しいという判断があったようです。当時とは時代も違いますし、企画がパワーダウンしてしまうことは避けられません。
HIP:工藤さんご自身は、『ギルガメッシュFIGHT(以下、ギルガメF)』のプロデューサーの打診があったとき、どのように受け止めましたか?
工藤: 話をもらったときは、単純に面白そうだなと。『ギルガメ』が放送されていた当時、私は小学校高学年から中学生・高校生という年代で、番組の存在は知っていたのですが、しっかり観ていたわけではありません。
でも、なんとなく、あの番組にはテレビ東京のいまに続く「手づくり感的DNA」が潜んでいるのではないかと思ったんです。ただ、描き方が非常に難しいとも思いました。地上波ではなくParaviでの配信になるとはいえ、勘違いしてはいけないなと。
HIP:勘違い、というと?
工藤:「配信=攻められる」みたいなイメージってあると思うんですけど、そこを履き違えて「攻める=肌の露出を増やす」とか、ただ単に過激にするみたいな方向性にはしたくなかったんです。もちろん、ドラマとして必要な露出であればいいんですけど、攻めるってそういうことだけじゃないはずですから。
私たちが最も描きたかったのは、深夜の低予算という悪条件のなか、いかに番組がつくられたのか。現場の熱量や、無理難題にどう答えたのか。お色気が先行して、そこがスポイルしてしまうことは避けたかったですね。

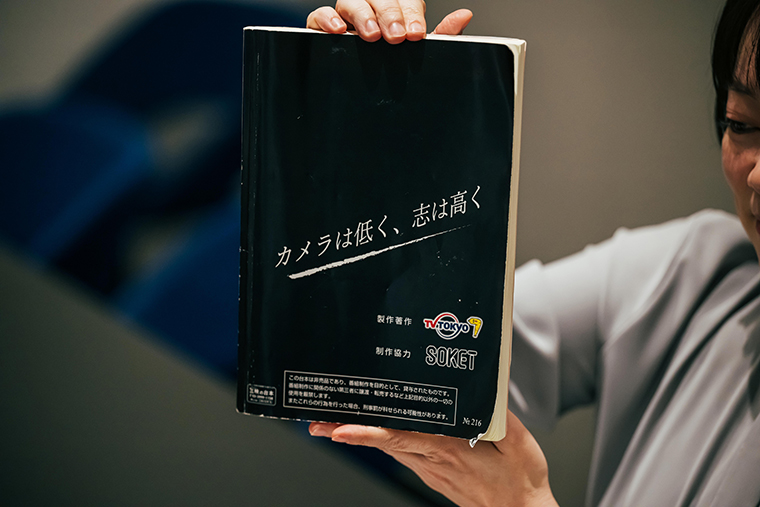
配慮から生まれた「裸エプロン用のエプロン」
HIP:とはいえ、『ギルガメ』を描く以上、過激さや露出は避けてとおれません。
工藤:いかに見せるのか、演じる俳優さんはどう感じるか、抵抗がある場合はどんなかたちで表現するのか、そこをしっかり考えましたね。
少なくとも、演じる側が本当はやりたくないのに、現場の空気やノリに押されて撮影が強行されるようなことがないようにしたかったんです。
HIP:際どいシーンを撮る際には演者の方と十分にコミュニケーションをとるなど、演者の意に反する見せ方にならないよう気を配るということでしょうか?
工藤:そうですね。たとえば、1話には公園でカップルがイチャイチャするシーンがありました。台本には「加藤竜也(主人公)が受付嬢の明菜と激しくキスをする。さらに、加藤が明菜の服を脱がそうとする」と書いてある。
しかし激しいキスと言っても、唇を熱烈に合わせるのか、舌が入るのか。服を脱がそうとするけど、肌のどこかははだけるのか、脱がそうとするのは具体的に服のどの部分でどこまでめくれるのか。人によって解釈が違います。
現場に来てみると自分の思っていた加減と違っても、監督の要求に応えよう、良いものをつくろうという責任感から「NO」と言いづらくなってしまうことがあるかもしれません。
HIP:たしかにありそうです。
工藤:『ギルガメF』においては、そういうことがないようにしたかった。衣装合わせでは俳優陣と監督を交え、具体的表現を丁寧に話し合い、その場で結論が出せないものは持ち帰り、プロデューサーサイドから撮影までにマネージャーさんに懸念事項をお伝えするようにしました。
私もなんでも気軽に相談してもらえる役回りになろうと考え、演者さんたちとコミュニケーションをとっていました。結果、本人が「大丈夫」と言っても、マネージャーさんに「本当に大丈夫ですか? 気になることがあれば気軽に言ってくださいね」とお伝えしていました。

HIP:そこまで丁寧にケアをしていたんですね。ただ、それでいて、当時あったお色気企画も変にぼかしていないというか、しっかり再現されていますよね。
工藤:『ギルガメ』の「裸エプロン」が、ドラマでは「水着エプロン」になっていたら違和感がありますよね。事実とも違いますし。裸エプロンは、やはり裸エプロンとして描きたい。じゃあ、いまの時代に合った裸エプロンってどういうものなのか、演者さんや衣装部と相談しながら考えようと。
最終的には、エプロンの腰を結ぶ紐とリボンの位置が絶妙で、見えちゃいけないところは見えないけど見せたいところは見せる「裸エプロン用のエプロン」をつくりました。裸エプロンに限らず、事実を大きく曲げないかたちでいまの時代に合わせた表現ができないか考えることが、『ギルガメF』ではとても大事なポイントだったと思います。

『ギルガメ』を世に知らしめた伝説の人物
HIP:ドラマのストーリーについては、どのようにつくり上げていきましたか?
工藤:当時のプロデューサー、ディレクター、アシスタントディレクターさんなど、『ギルガメ』の関係者一人ひとりに「OB訪問」をしてエピソードを聞いてまわり、つくっていきました。30年前ですから、すでにテレビ東京を退職されている方もいたのですが、連絡先を知っている社内の人間につないでもらって。
HIP:ドラマに出てくるエピソードも、ある程度は事実に基づいている?
工藤:関係者からリサーチした内容をモチーフにしていますが、もちろんすべてが事実ではなく、エンタメとして脚色している部分もあります。ただ、主人公のディレクター・演出の加藤竜也(演・藤原季節)の多くの部分を参考にした人物はいて、それが佐藤哲也さんという方です。

HIP:ドラマではテンガロンハットを被っていましたね。
工藤:実際にいつも被っていました。個性的な人で、局内でも「『ギルガメ』といえば哲也さん」と、なかば伝説のようになっていました。
でも、調べてみると『ギルガメ』の約8年の歴史のなかで、佐藤さんがディレクターを担当していたのは3か月だけなんです。そんな人が、いまでも番組の象徴のように語られている。その背景を紐解きながら、ドラマに落とし込んでいきました。





