成否を決めるメンバー選考。営業系に白羽の矢を立てたワケ
HIP:2018年5月に奈良岡さんがシリコンバレーに派遣され、3か月後の8月にブートキャンプ一期生が送り込まれました。枠は限られていたと思うので、人選がかなり重要になってきますよね。
奈良岡:はい。ただ、ブートキャンプ自体がはじめての取り組みだったので、人選を含めて手探り状態でスタートさせたというのが実情です。
そのなかで、第一期は営業系の部長たちなど約20名をシリコンバレーに呼び、1週間ほどの研修を受けてもらいました。そのうちの1人が、後にRUN de Markを立ち上げる杉山です。

HIP:なぜ営業系の部長を初期メンバーに選定したのでしょうか?
奈良岡:2つ理由があります。まず、基本ノリがよく、前向きなタイプが多いということ。ここで持ち帰ったものを社内に伝播させるのに、一役買ってくれるだろうという期待がありました。
もう一つは当時、営業系の若手の離職率が高かったことです。いまの若い人たちはスマホ中心の生活をしています。そんななかでわざわざ新聞やテレビの会社に入社する人には、既存のメディアを「自分たちの世代に合うかたちに変えていきたい」という意識があるわけです。特に、営業系の若手にはそうした思いが強くありました。
ところが、それを提案しても部長級の壁が厚くて通らない。結果、会社に見切りをつけて辞めていくパターンが多かったんです。ならば、まずは彼らの上司にあたる世代の意識を変えないといけないだろうと考えました。
HIP:実際のところ、意識は変わりましたか?
奈良岡:そうですね。最初は懐疑的だった一期生たちも、いい意味でシリコンバレーにかぶれてくれました。部長たちのマインドセットが変わり、発言や行動が変わったことに若手も気づき始めたところで、すかさず第二期のブートキャンプを仕掛けたんです。今度は公募というかたちで、やる気がある若手や中堅を中心に20人ほど集めました。
HIP:そのうちの一人が、萩原さんですね。なぜ手を挙げたのでしょうか?
萩原諒氏(以下、萩原):ブートキャンプ一期生の話が持ち上がった当時、東京支社で営業をしていたのですが、まさに先ほど奈良岡が言ったような、会社にネガティブな感情をもつ若手社員の1人でした。入社10年目を迎え、この先も会社の現状は変わらないだろうと思っていたし、新しいことをやりたい気持ちが強くなっていました。
そんなときにシリコンバレーの話を聞きつけて、面白そうだな、自分も行きたいと思いました。最初はミーハーな気持ちでしたね(笑)。そこで、すでに駐在が決まっていた奈良岡に、それとなく一期生で行きたいとアピールしました。

HIP:しかし、一期生には選定されなかった。
萩原:はい。絶対に呼ばれると思っていたので、フラストレーションが溜まりましたね(笑)。そのときに、あらためて会社の現状や、それに対して自分は何ができるのかについて設計図を描き、第二期の公募が始まった瞬間にエントリーしました。
HIP:実際に行ってみて、自身のどこが一番変わったと思いますか?
萩原:もちろんデザイン思考やシリコンバレーのカルチャーを学べたのも良かったのですが、個人的に一番の発見は、自分と同じ思いを持つ仲間と出会えたことですね。
二期生には報道や編集など他部署の人も多かったのですが、みんな会社に対する危機感を持ち、なんとか変えていこうという思いを抱いていました。そのメンバーたちと熱い話を交わせたことで、帰国してから周囲に何を言われても、「仲間がいる」と信じて既存事業の変革や新規事業創出に取り組むことができたように思います。

第三期で「本丸」に照準。キーマンのマインドセットに成功して変革が加速
HIP:しかし、いくら営業や意欲ある若手の意識が変わっても、新聞やテレビなどの既存事業に取り組む人たちを動かさないと、なかなか変革は難しいように思います。
奈良岡:私たちも、そこが「本丸」だと考えていました。会社のメインどころである新聞の編集局やテレビの報道制作局・編成業務局の意識を変えないと、会社は変わらない。そこで、第三期のブートキャンプには編集局・報道制作局・編成業務局の部長たちに参加してもらいました。
ただ、彼らは社内での影響力が大きいだけに、ここでしくじると良からぬ噂が広がってしまう。「シリコンバレー、たいしたことないよね」なんて言われてしまうと、変革が厳しくなってしまいます。ですから、第三期の研修はものすごく力を入れました。
新聞やテレビなどの既存事業は、長年にわたって会社を支えてきた屋台骨。数多くのノウハウが蓄積され、多くの社員に受け継がれてきました。
しかし、メディアのあり方も常に変化し続ける時代。これからは、「正解がある世の中」(ビフォアーインターネット)から、「誰も正解がわからない世の中」(アフターインターネット)へのシフトが求められるのです。
研修の結果、三期生もシリコンバレーのカルチャーに触れ、なんとか、アフターインターネットの価値観に変わってくれた。既存事業変革のキーマンのマインドセットが成功したことで、新規事業や既存事業の変革の話が進めやすくなりましたね。

105ページにわたる経営層への提言。「イノベーションリポート」作成に込められた思いと狙い
HIP:2019年4月には、新規事業を創出するオフェンシブチーム、既存事業の変革に取り組むディフェンシブチーム(後にビジョニングチームに改称)に分け、それぞれの活動も始まりました。ブートキャンプの卒業生の発案で始まったのが2020年8月に発表した「静岡新聞社イノベーションリポート」ですね。
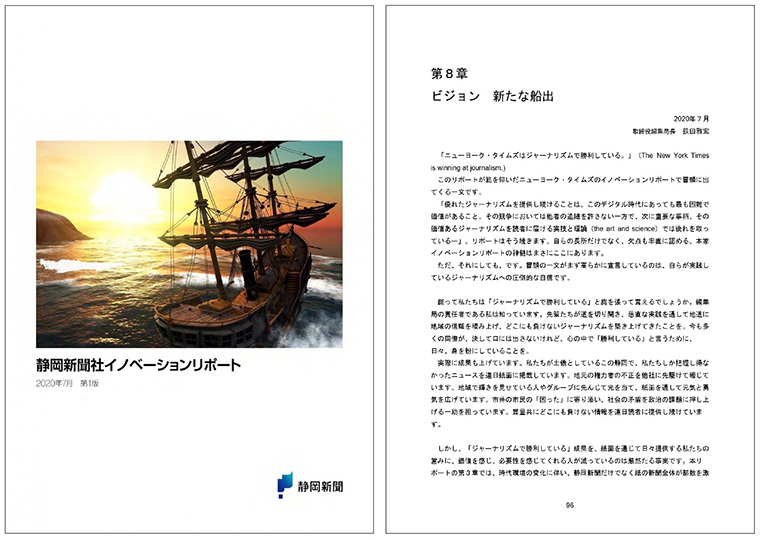
奈良岡:はい。主にビジョニングチームのメンバーで制作した「静岡新聞社イノベーションリポート」は、ニューヨークタイムズ(NYT)のイノベーションリポートのつくり方にならったもので、静岡新聞社の現状やポジション、ユーザーが求めているもの、さらにそこにあるギャップを埋めるための方策などの提案を行い、静岡新聞社のあるべき姿を描き出しています。
HIP:「イノベーションリポート」は全105ページの大部で、制作にはじつに1年以上も費やされたそうですね。とても大がかりな取り組みですが、その狙いはどこにあったのでしょうか?
奈良岡:私たちが参考にしたNYTのイノベーションリポートもまた、既存事業の組織と戦略を変革させることを目的としたものでした。その後NYTは見事に変革を遂げ、デジタルメディアに生まれ変わった。
一方、私たちが「イノベーションリポート」作成に際して重要視したのは、既存事業を変革するにしても、まずは自分たちの「現在地」を確認すること。社員と社外の関係者(生活者、キーマン)に共感インタビューし、静岡新聞社に対する「社内の自己評価」と「社外の評価」のギャップをあぶり出し、静岡新聞社の10年後の将来と現在の「変えるべき所」「変えるべきでない所」の定義を試みました。
そこでたどり着いた答えが「ユーザーファースト」。リポートの最後にも「ユーザーファーストで、変わり続けるのが当たり前の企業文化を身につける」と書きました。
アフターインターネットの世界では、もはや「マス」は存在しないと考えています。ユーザー一人ひとりに寄り添いながら、彼・彼女らが必要とする情報を届けて課題を解決するのがわれわれの役目です。
HIP:そうして作成された「イノベーションリポート」は社内にとどまらず、社外にも発表されましたね。
奈良岡:NYTのイノベーションリポートはもともと社内向けにつくられたものがリークされて社外に広まった。一方当社の「イノベーションリポート」は最初から社外に発表した。ここには当社の「覚悟」を表明するという意味合いもあります。
一方、社内的には、社員や経営層に向けた変革のメッセージであると同時に、社員・読者への共感インタビューをはじめとした長期にわたる制作過程から、社員一人ひとりの意識改革につなげる狙いもありました。
HIP:まさに、会社がイノベーションするためには、まずは自分が変わらないといけないという「自分ごと化」ですね。
奈良岡:そうです。リポート発表から数か月経った現在、徐々にですが、マインドセットの変化を感じています。ユーザーファーストと自分ごと化が浸透しつつありますね。
実際に、RUN de Markは、メディア事業とは無関係の事業に見えますが、ユーザーの声を聞き、課題をすくい上げて解決するために生まれたアプリという意味と、コミュニティのあるところにメディアが必要になるという、本来メディアがあるべき姿につながるという意味で、当社のこれからのビジョンを体現した事例といえます。

変わりつつある社内の雰囲気。ユーザーに向かい合うことで課題を解決する
HIP:杉山さんは実際に、現業と並行してRUN de Markを立ち上げられたわけですが、その際に社内の雰囲気の変化などは感じましたか?
杉山:はい。新しいことにチャレンジできる土壌は確実に醸成されてきています。
じつは、RUN de Markの開発が佳境にさしかかっているとき、現業と兼務なので時間をつくる大変さに悩んでいました。特にサービスのローンチ(2020年10月)の2か月前までは外勤営業だったため、数字はしっかりつくらないといけない。
ただ、逆に言えば数字さえ出せば、他の時間で何をしていても許されるんです。いい意味で、放置してくれる。それは、やはりブートキャンプの一期生に営業系の管理職が多かったことも大きかったと思います。現業の営業活動とはまったく関係ない、RUN de Markのための出張なども許してくれましたから。
やる気さえあればトライさせてもらえる環境は確実に整ってきているし、とてもやりがいを感じますね。

HIP:今後、RUN de Markをどんなサービスにしていきたいですか?
杉山:大きく掲げているのは「すべての人の心と体を健康に」という目標です。ランニングは体の健康はもちろん、走っている間にいろいろなことをリセットできます。それを続けるためには、誰かと「共に走る」こと。競う競走ではなく「共走」がとても大事です。ですから、当面はペーサーの数を増やしつつ、イベントやオンラインミーティングなども積極的に行ってコミュニティの輪を広げていきたいですね。
萩原:もともとランニングアプリを始めたのも、「ユーザーに共感して、その人の課題を解決する」という考え方がベースにあります。RUN de Markはランナーの悩みを解決するサービスですが、既存事業の新聞やテレビの変革も根底は同じ。ジャンルを問わず、徹底的にユーザーと向き合い、彼らのやりたいことを叶える。そのそばにわれわれが寄り添いたい、と考えています。
奈良岡:生活者起点に立ち、自分たちが変わり続けるため、これからわれわれ社員はユーザーインタビューなどを通して、個別の課題に向き合う「クセ」を身につけなければならないし、マインドセットのさらなる変革も必須です。その能力を培うためにも、RUN de Markに続く新規事業をどんどん推し進めていきたいですね。

ARCHで新規事業の取り組みを加速。他社とのコラボも計画
HIP:現在、新規事業創出をミッションに掲げる組織が集まるインキュベーションセンター「ARCH(アーチ)」にも会員企業として参画していますね。参画理由と、ARCHに期待することを教えてください。

萩原:これまで当社ではイノベーションの専門部署をつくってこなかった。そのため、ARCHは本当の意味で静岡新聞社にとっての「出島」になるかもしれないと考えています。新規事業を創出するためには、オープンイノベーションが必要ですし、いろいろな価値観を持った方々と接点をつくることも大切です。ARCHはその意味で、非常にいい環境だなと。
まだ入居して間もないのですが、他社の方々と気軽に話し合える機会を得られています。実際に、いくつかの企業とのコラボも決まっています。ARCHでのコミュニティを活用すれば、より一層新規事業の取り組みを拡大できると期待しています。






