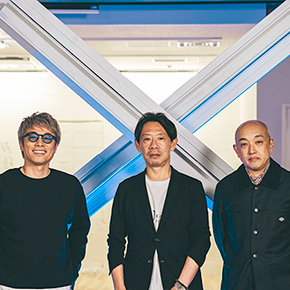新たな主力事業の軸となる「カーボンニュートラル」「デジタル社会」と、研究開発から商品開花へつなげる組織づくり
HIP:立ち上げに至り、地域新電力に対する社内の反応はいかがでしたか?
伊藤:碍子(がいし。電線や変電所など送電網で電気を外に漏らさないためのセラミック製品)業でスタートした当社ですが、あらゆる事業へと多角化を進めてきました。そうしたなかで、今日に至る当社の主力製品は碍子から、自動車の排ガスを浄化するセラミック製品へと転換していきました。
しかし、ご存じの通りEV化の波が到来し、そのセラミック製品もいずれピークアウトしていくことは目に見えています。そこで当社は現在を第三の創業と位置付け、カーボンニュートラルとデジタル社会を今後の成長分野として事業転換を図っています。
今回の恵那電力はまさしくカーボンニュートラルと大きく関連する新規事業です。変革をあらわすようなケーススタディーであることから、社長報奨の奨励賞をもらい、先進事例に挙げられるまでに注目度は上がりました。
HIP: そのほかに貴社内で取り組まれている新規事業の進め方について教えてください。
中西:2022年4月に「NV推進本部」という新組織が立ち上がりました。NVとはNew Valueのことで、新製品や新規事業の早期創出のため、開発の初期段階からマーケティングに関与し、推進して、ビジネスにつなげていくことがミッションです。「技術を生み出したはいいが、お客さまがいない」という状態を脱却すべく、商品開発までつなげていく役割です。
また当社は昨年、2050年を見据えた「NGKグループビジョン Road to 2050」を策定し、その実現のために5つの変革に取り組んでいます。そのなかには「商品開花」(新たなプロダクトが商品として花開き、社会実装されること)、「ESG経営」(事業での社会課題解決)などが含まれており、さまざまな活動がスタートしています。
これまで名古屋にしかなかったパートナーとの共創を推進するための拠点「ID-Room」を東京にも開設し、オープンイノベーションを加速させています。

モノ売りからコト売りへ。大切な視点は、いかに価値を生み出すか
HIP:お二人が今回の地域新電力事業の取り組みを通じて得た気づきとは何だったのでしょうか?
中西:新規事業と聞くと、ビジネスモデルが理にかなっているかどうかとか、アイデア勝負だとか思われがちですが、それ以上に大切なのは「やってやるぞ」という情熱に尽きると思います。
その過程では傷つくこともあれば、非難されることもあるでしょう。それでも私たちは絶対に実現させるんだという強い気持ちがあったからこそ、企画から1年という短期集中戦で事業化に成功したのではないかと振り返ってみて感じます。
伊藤:扱うビジネスがモノからコトに変わったわけですが、コトに価値を見出すという考え方はステークホルダーと話すなかでつねに求められていましたし、そのうちにわれわれの感覚も鋭くなってきたのだと思います。
そうした視点の切り替えも大切です。お客さまが必要なのは蓄電池(モノ)ではなくて、電気をためるコト、極端なことをいってしまえば、われわれがつくるNAS電池じゃなくてもよくて、それが仮にリチウムイオン電池であってもいい。
大切なのは、いかに価値をつくり出すかということ。さらに見出した価値を自社の製品やサービスの開発にフィードバックすること。それが今後の私の課題であり、実現したいことでもあります。

HIP:恵那をロールモデル(=恵那モデル)としたうえで、北海道網走市でも地域新電力を設立したとうかがっています。最後に現状の課題を踏まえ、お二人が仕掛ける次の一手を教えてもらえますか?
中西:まず、恵那電力目線でお話しすると当然、目下の目標はいかに自主電源を確保して地産地消率を高めるか。さらにこれを、経営の安定性を損なわない程度に、かつ環境に負荷を与えないように、住民の理解を得つつ事業にインパクトを与えていくこと。これが、今後実現したいビジョンです。
次に日本ガイシ目線でお話しすると、恵那電力をロールモデルとし「地域新電力を使うとこんないいことができるんだ、日本ガイシと組むとこんなことができるんだ」と、日本全国の自治体に思ってもらえるようなブランド力を向上させていくことが目標です。
直近では、リコーさまやIHIさま、岐阜大学さまと産学連携での実証実験や共同研究を開始したように、多様なステークホルダーの目線を集められるような地域新電力に育てていくことが私たちのミッション。
いま伊藤がいったように、必ずしもNAS電池を使った供給網である必要はなく、大切なのは地域新電力という「コト」を提供し、それが受け入れられるようにすることです。ゆくゆくは、日本全国展開を目指し、挑戦を続けていきたいです。