アートとテクノロジーの祭典『Media Ambition Tokyo(以下、MAT)』が2013年の開催から今年で10年目を迎える。チームラボやライゾマティクスをはじめ、著名・気鋭のアーティストによる作品が公開され、それとともに開催期間中には多くのトークセッションも行われる、あらゆる発信が行われる場だ。最先端のアートや映像、音楽、パフォーマンスなどが集結した同イベントはどのように都市に実装され、今後どのような世界を描くのか。
その軌跡から新規事業を成功させるためのヒントに至るまでを、MAT代表理事でありJTQ代表として数々の空間デザインを手掛けてきた谷川じゅんじ氏に訊く。聞き手は、MAT創設メンバーの森ビル・杉山央が務めた。
文:桐生幹太 写真:玉村敬太
原点は家具の祭典『ミラノサローネ』。場の熱気に憧れ、悔しかった
杉山央氏(以下、杉山):まず、読者の方に向けて、MATの概要やコンセプトからお話いただけますでしょうか。
谷川じゅんじ氏(以下、谷川):MATは都市を舞台に、最先端のテクノロジーカルチャーを実験的にお披露目するリアルショーケースのような祭典です。名前の由来も、「自分たちが見せたい作品を集めて東京で見せよう」という意味からつけられました。いまでもそのコンセプトは変わっていません。2013年にスタートしたとき、記者発表で配ったステートメントの冒頭にはこう書いています。
【Media Ambition Tokyo[MAT]は最先端のテクノロジーカルチャーを実験的なアプローチで都市実装するリアルショーケースです。Media Ambition Tokyo[MAT]は民間による民間のための全く新しいテクノロジーカルチャーイベントです。
テクノロジーアートを都市へ実装する実験的展示プログラムや新しい集客モデルの提案、新たな視点やコンセプトに基づく新規事業モデルの開発をも視野に入れた新しい時代のアクチュアルコミュニケーションプログラムです】
これはいま振り返ると、MATのパーパスであり、現在まで一貫して続いているものです。

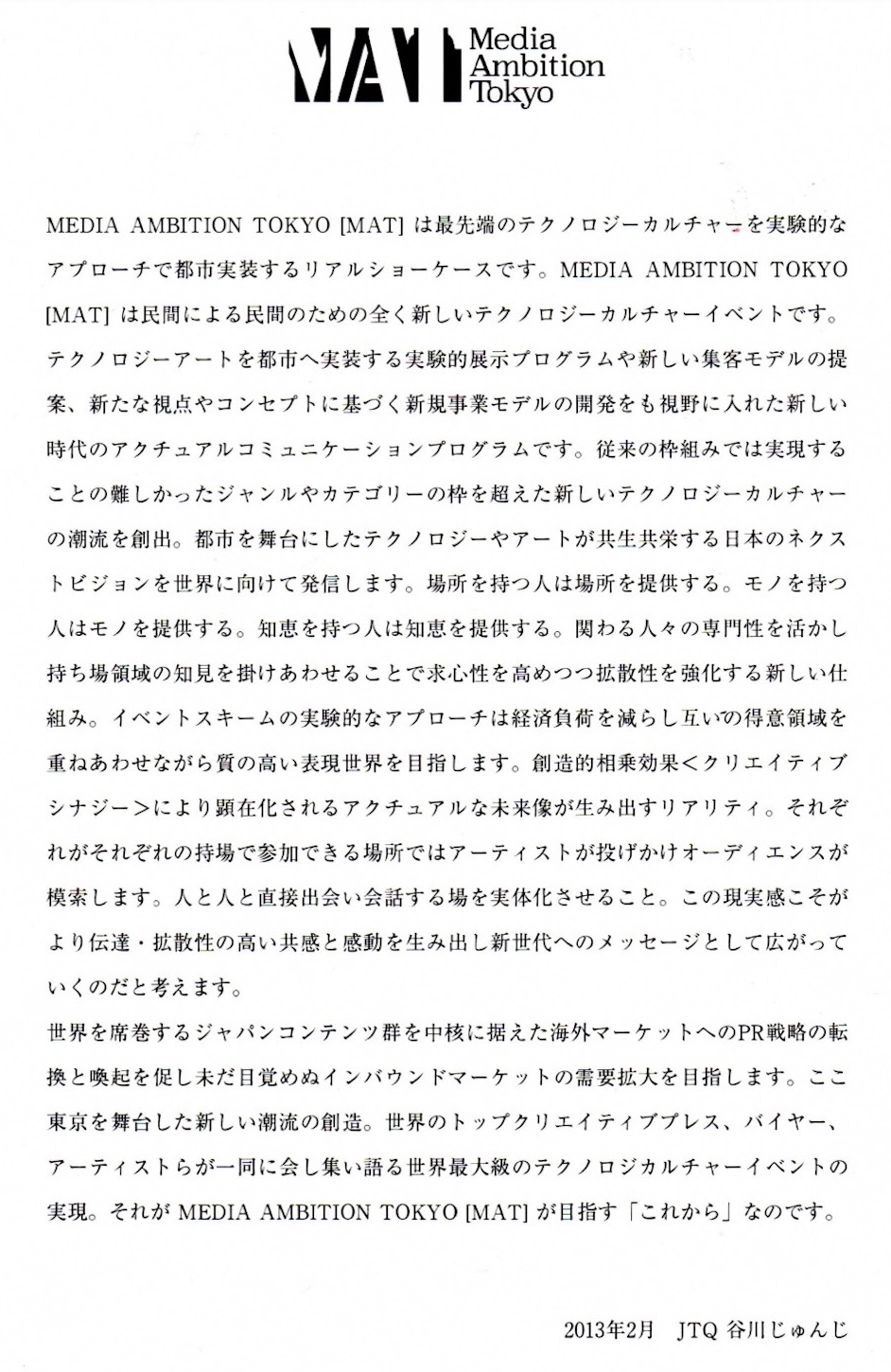
谷川:そもそもステートメントに書いたMATの原型は、世界最大規模の家具の見本市『ミラノサローネ』なんですよ。2000年代初頭の『ミラノサローネ』は東京の3分の1弱くらいの面積であるミラノ市に、世界中からデザイナー、PR、リサーチャーら40万人以上が集まっていました。
ビジネスを動かすことのできるそれだけの人たちが、エネルギーを抱えた状態で一堂に会するから、化学反応が起きて一気にいろんなことが起こる。会場のパビリオンから次の流行情報が出てくるだけでなく、ミラノ市街でも数百ものイベントを行なわれていて5日間の会期中に何回もバズる。すると「これはすごい」と、その人や商品が話題になって一気に評価が高まる。さらに、今年の新作や数年先のトレンドを見据えたプロトタイプが発表され、また名の売れていないつくり手による野心的な作品もあり、非常に重層的な場になっています。
『ミラノサローネ』の持つそうした熱気にぼくはすごく憧れていたし、悔しかったんですよ。日本には同じような熱量のイベントが1つもなかったですから。当時のぼくは、「なぜ、東京のインフラを生かし、みんなで一枚岩になり世界中から人を呼ぶ仕掛けを考えないんだ」「オーガナイザーは何をしているのか」など思っていて、イライラがピークに達していたんです。
杉山:その頃、谷川さんとは別の仕事でご一緒していましたが、ある日「六本木ヒルズ52階の展望台(東京シティビュー)で祭典をやりたい」と相談に来られたのを覚えています。思えば、そこからMATの企画につながっていきましたね。


初回の大盛況と、2回目の大赤字。失敗を経て気づいたMATの価値とは
杉山:あのとき、なぜ東京シティビューを選ばれたのか、あらためてお話しいただけますか。
谷川:もともとぼくは、六本木にある国立新美術館で開催される『文化庁メディア芸術祭』の空間構成をやっていました。会場の広さに制限があるから、受賞作品を映像展示せざるを得なくて。期間中には海外アーティストも来日してくれてたけど 開館時間以外にこれといったプログラムもなくて。もっとつながれたらいいのになと。
『ミラノサローネ』では、夜になるとレセプションが開催されていろんな人たちと出会う機会があるのに、これではもったいない。だったらアーティストを呼んでコラボレーションできないかって齋藤精一さんなんかと話していました。
その時期、いろいろ調べてみると、メディアアートと呼ばれる領域で活動する多くのアーティストが、『文化庁メディア芸術祭』と同時期に独自イベントを開催していたことがわかって。その数都内だけで30、40か所あったんです。これらをつなぎ、メディアアートの領域に関わる人たちで集まれる場、つまり『ミラノサローネ』のような連帯を日本にもつくろうと企画したのがMATの出発点です。
初回を3日開催だったんですが、メディアアート、テクノロジーという分野の特性からか感度の高い人が予想以上に集まったんです。日本では初公開となるチームラボの展示やエンタメを素材にしたライゾマティクスの作品のほか、メディアアートと映像、音楽など異なるジャンルのコラボアーティストライブ、大御所も若手も混ざり合って、本当に面白いイベントになりました。森ビルも含めて、関係者も手応え感じて非常に喜んでくれました。
杉山:それで翌年以降もやってみようと。
谷川:はい。ただ、翌年は期間を延ばして約2か月間実施しましたが、もう大赤字(笑)。でも同時に、MATは最初のステートメントに書かれた理想が実現されていったことが理解されて、パートナー企業も増えていった。それで森ビルのように場所を持っているなら場所を提供する、メーカーさんであれば物品提供でプレイスメント、そしてクリエイターは作品やアイデアを持ち込むという創造的な生態系がゆるやかに生まれたんです。
杉山:ローコストでも面白いものが集まる状況がつくられていきましたよね。
谷川:『ミラノサローネ』でも、日本の企業はブランディングのためにかなりのコストをかけて出張っていたのですが、海外インテリアメゾンは、地の利を活かしスマートで話題性のある発信を、工夫して実に合理的にやっていたんですね。パーマネントとテンポラルな環境も上手に組み合わせて印象づけるアプローチは本当に勉強になりました。
人が惹きつけられるのは、そこに集まる人や情報といった「その場に行かないと体験できないない価値」対して人は反応します。それを東京という実空間に実装し続ける。それこそが2013年から継続しているMATのマニフェストなんです。2018年に一般社団法人化したのも、運動体としてより持続性を高めていこうと考えたからです。

杉山:森ビルもMATの発足当初から、そうした谷川さんのビジョンに強く共感していますし、もともと私たちには「街づくりには文化やアートが必要だ」という思想がありました。これからますます選ばれる街や都市の価値として、駅距離や建物のスペックではなく、そこにどんな人がいて、どういう出会いやコミュニティーが必要なのかというのは、より重要な要素になってくるでしょう。





